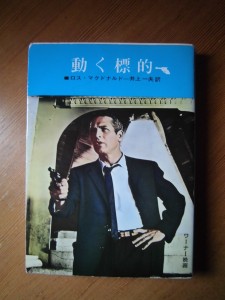窓ガラスの汚れ、ピースとハイライト 2015年元旦
金曜日, 1月 2nd, 2015
大晦日に自宅のガラス窓を拭いた。最初に外側から布で拭いて汚れをとる。つぎに内側から汚れを拭き取る。それでもよく見るとまだ汚れている。外から拭くと、あれ?汚れが落ちない! 汚れているのは内側なのか。いや、やっぱり外側か。
ガラスの汚れの原因が内か外かを見極めるのは実にむずかしい。ふと、これは人と人との議論や意見の違いと似ていると気づいた。ぶつかり合ったとき、互いにその原因は相手にあると考えて、自分が正しいと主張する。だが、ガラス窓の汚れの原因がどちらの側にあるのかわからないように、誤りは自分の側にあるかもしれないのだ。
自己の正当性を声高に主張する、つまり自分の側のガラスは汚れていないと言い張る議論がここ数年際立っているような気がする。
この夜、NHK紅白歌合戦で、久しぶりに登場したサザンオールスターズ。桑田佳祐の歌う「ピースとハイライト」の歌詞が意味深だ。
♪ 今までどんなに対話(はな)しても
それぞれの主張は変わらない。
♪ いろんな事情があるけれど
知ろうよ互いのイイところ
自分の主張の正しさを譲らずに、意見を戦わせる。いくら対話をしても主張は変わらない。でも、違いをみとめて、相手がなぜそういうことをいうのか、相手の事情やいいところも理解しようとしてみたらろうだろう。そんな気持ちをやさしく訴える。
理想主義と言えばそれまでだが、いつからか、理想を掲げる人を「甘っちょろい」とか、「現実を見ていない」と、見下すような風潮がある。確かに理想だけを標榜して、それに至る現実的なプロセスを考えない意見は弱い。しかし、問題に対峙した時、理想のない対応策は、力のない淋しい現実主義とはいえないだろうか。
桑田は、ポップなメロディーにのせて時々、社会的な言葉をのせる。音楽のもつ力を発揮して、わかりやすい言葉で理想を語る。人々にまずは互いを知り合うようにと。切なく、セクシーな言葉とメロディーが真髄のサザンには、こういうサウンドもあるのだ。
ますます世の中は、自分と意見の異なる世界へ不寛容になっている。もう一度原点に立ち返って腹を割って語り合ってみようというサザンのメッセージは、この時代に意味が深い。嫌いなやつや意見が合わないやつはいる。でも、どうして相手はそう考えるのか、まずは考えてみたらどうだろう。
ガラスの汚れから桑田の歌へ。そして明けて2015年。ガラスの汚れを落とすように、対立は時折立場をかえて原因を探ってみたいものだ。(敬称略)