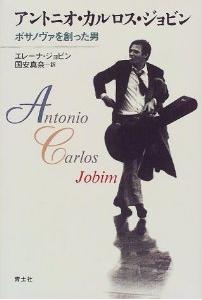後藤健二さんの最後の気持ちを想像すると、ただ胸が詰まる。イスラムの敵ではなく理解しようとしてきたジャーナリストとして誠実に行動してきた人間を、死の恐怖に陥れ、そして殺害するという行為を非難しようとすれば、怒りで汚らしい言葉しか見つからない。
では、この怒りを越えて、何ができるか、何をしなければならないか。それは後藤さん、湯川さんの二人の死をどう教訓として生かすかを冷静に考えることではないか。安倍首相は、この行為に対して償わせると言った。
犯罪を行ったものへの償いをさせることに異論はない。強力な特殊部隊などが仮にいたとしたら、イスラム国に潜入し、犯人に天誅を下してほしいくらいだ。ただし、イスラム国だけに限った償いをさせることができるとしたらである。
アメリカや有志連合による空爆をはじめ、対イスラム制裁の軍事行動を強化した時、イスラム国の出方によっては民間人に犠牲者がでることは十分考えられる。後藤さんらとおなじように死に、後藤さんの家族と同じように悲しむ人がたくさんでることになる。
さらに言えば、後藤さんはある使命感と覚悟をもって自ら危険地帯へ赴いたはずだ。これに対して攻撃にさらされた地に暮らすような人々の不幸は、まったく意味も分からず突然訪れるものであり、自分の意思とは関係のないところでただ殺されることになる。そうした事態を招くことは後藤さんの望んでいたようなことではないだろう。
時代を少し遡ってみよう。2001年の9.11以降に、アメリカが行ったタリバン攻撃のためのアフガニスタン空爆、2003年からのイラク戦争で、誤爆などによりいったい関係のない一般市民がどれだけ死んだことか。
2002年7月1日には、アフガン南部への米軍空爆で、結婚披露宴中の人たちを含む民間人が少なくとも48人死亡した。アメリカは「それは事故だ」と、誤爆であることを認めた。これはほんの一例である。
イラク戦争では、アメリカがファルージャ掃討作戦を始めた2004年4月5日から6月3日までの間で戦闘やテロで死亡したイラク人は1100人以上であると当時イラク保健省がまとめている。このうち14歳以下の子供も81人含まれる。これでも一部である。
空爆や市街地での地上戦などを行えば民間人に犠牲がでるのは明らかである。しかしそれがわかっていて実行する。それを日本政府は積極的に支援した。その政府を選んだわれわれは、「正義の戦い」による誤爆によって、まったく戦闘と関係のない民間人が多数死んでも仕方がないと思っていたことになる。
だとすれば犠牲者の遺族は、どう思うだろうか。後藤さんや湯川さんの遺族が悲しむように、多数の人が憤り悲しみ、その怒りの矛先がアメリカとその同盟国、そしてその国民に向いたとしても仕方がないことは、彼らの立場に自分を置いてみればたやすく想像できることだ。つまりわれわれは誤爆などについては間接的に加害者の立場にいる。
そんなことを言っても、日本人全体をいまやターゲットにしているといっているのだから、殲滅しなければ国民、国家が危険にさらされる、という声がかならずでてくる。物事を単純化すればその通りだ。また、単純化は理解されやすい。だがそれは、ただ自分の身が危ないから、まず何とかしたいといっているに過ぎない。それによって誰かが傷ついたとしても見て見ぬふりをする、あるいは考えないという姿勢だ。イスラム国と同様とまではいわないが、似たようなものだ。
では、どうするのか。簡単にはわからない。しかし、まったく誰も傷つけないことは不可能だとしても、最小限に抑えながらイスラム国を弱体化し殲滅に追い込む方法を徹底的に議論してみたらどうだろう。今回、後藤さんを救出するために世界各地でインターネットなどを通じてメッセージが広がった。
こうした手段をつかって、彼らの言語で、いかに彼らが罪深きことをしたかということを健全なイスラム社会の力を借りて世界に発信し続けることなども一つだろう。彼らがいかに非道なことをしたか、後藤さんという貴重な人材を失ったことをわれわれの悲しみや怒りが、イスラム国の人間よりはるかに大きいかを延々と知らしめることだ。
なにやら、自分たちが被害者で、怒りをもって正義を行使するようなことを言っている彼らに、もっと激しい怒りをもって対処することだ。
罪深い、非道な相手に償わせるのはいい。だが、安易な方法で敵対方法にでて、われわれもまた償いを背負うような側に立つことは避けたい。この際、後藤さんだったらどうしただろうか、いま、天国でどうしてほしいと思っているか。それを考えてみようではないか。そしてじっくりイデオロギーを超えて議論を煮詰めてみたらどうだろう。
※ ※
湯川遥菜さんの父親が、後藤さんの死を知り嗚咽していた。息子を殺された悲しみと、息子を助けに行った人が殺されたことへの申し訳なさと悲しみ。息子が人質になったときに、自分の育て方が悪かったと詫びていたが、いったいこの父親になんの謝るべき理由があるのだろう。湯川さんは立派な大人である。二重の悲しみを負ったこの人もまたまぎれもない被害者のひとりである。罪もない人を殺した側が何より責められることを忘れてはならない。